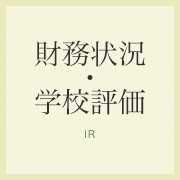令和6年度 浜松学芸中学校・高等学校【自己評価・学校関係者評価】結果報告書
| 校訓 | 学校目標・方針 | 目指す生徒像・学校像 | 評価 |
|---|---|---|---|
| 内観 受容 継続 |
|
*じっくり考え、よりよく判断し、ねばり強く行動する生徒 *地域・社会のために存続していく、魅力ある学校 |
A よくあてはまる(良い) B おおむねあてはまる(やや良い) C あまりあてはまらない (やや不十分) D まったくあてはまらない(不十分) |
| 評価領域 | 評価項目と具体的方策 | 自己評価 | 成果及び改善点 | 評価 | 学校関係者からの意見 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校経営 | 校訓を踏まえ、「じっくり考え,よりよく判断し、粘り強く行動する生徒」に育てるべく、愛語「温かく心のこもった言葉かけ」を通して個々の自立(自律)に伴走する。 | B | 温かな言葉かけは浸透しつつあるが、厳しさも含めて働きかけたい。 | A | 生徒・教員双方に向けて、手厚い対応に努めようとする姿勢を感じる。 |
| 教育課程 | 教育課程がより良いものになるように学校行事を精選し、行事日程や日課等の検証・検討・修正を図る。 | B | 年度ごとに行事や日課は見直されているが、業務過多な時期もある。 | A | 限られた条件の中で調整が図られ、工夫して行われていると思われる。 |
| 教科指導 | 「目指す授業像」に迫る授業を展開し、生徒と協働しながら「自立した学習者」を育成するように努める。 | B | 授業の工夫はみられるが、自立に結びつけるうえでの課題は多い。 | A | 生徒の立場を理解し、工夫されているが、個に沿った指導を更に求めたい。 |
| 進路指導 | 希望進路実現のために必要な情報を収集・発信し、生徒個々に伴走するように努める。 | A | 多くの職員が協力的に進路指導に関わる体制ができつつある。 | A | 学校が一丸となって取り組んでいる。今後も体制の強化を期待する。 |
| 生徒指導 | 問題行動の未然防止のため、生徒の小さな変化に目を向け、保健室・相談室等とも緊密に連絡を取り、日常的な情報交換に努める。 | B | 職員間で問題の共有に努めている。マナー指導に課題が多い。 | B | 挨拶に清々さを感じる。マナー面は継続的な指導に努めてほしい。 |
| 特別活動 | 探究・部活動を通して、生徒一人ひとりが自発的に考え、行動できるようにサポートする。 | B | 成長のための場と機会は整っている。委員会活動も工夫したい。 | A | 地域的な貢献活動が顕著である。部活動の充実に期待したい。 |
| 健康管理 | 定期健康診断・傷病予防・薬学講座・思春期教室等、生徒が心身ともに健康で安定した生活を送るための取り組みに努める。 | A | 保健室の取り組みを中心に健康や安全への関心が高まっている。 | A | 必要なことが計画的かつ着実に実施されており、高く評価できる。 |
| 安全指導 | 地震・台風・火災等、災害への対応について、マニュアルや緊急連絡システムを整備し、防災訓練等を実施して生徒の安全確保に努める。 | B | マニュアルや備蓄の見直しは図られた。実践的訓練を取り入れたい。 | B | 訓練的な活動は更に実践的になるように取り組むことを望む。 |
| 家庭との連携 | 学校の教育方針や教育活動について、保護者会・インターネットツール(ホームページ等)・学校案内・各種通信を通して、家庭や学校関係者・受験対象者等へ的確に伝えることに努める。 | A | 外部発信の機会が増え、内容的にも着実に質の向上がみられる。 | A | 質・量ともに年々充実してきており、外部からも好評を得ている。 |
| 地域との連携 | ときわ祭・体育祭・演奏会・作品展・各種行事および各コース活動を通して、本校への関心を高められるようにする。 | A | 各行事への来場者が多く、活気を感じる。地域との連携も始まっている。 | A | 工夫されたイベントや地元企業との積極的な連携は評判である。 |
| 他の教育活動 | 質の高い学習環境の実現のために、施設・設備の機能化・充実化を図る。 | B | 南館増築で活動場所が充実した。旧館のメンテナンスに課題が残る。 | A | 新館の設備は素晴らしい。旧館の老朽化対策へも配慮が必要である。 |
今後に向けての学校の考え(学校関係者評価を受けて)
進路指導の成果や外部発信の充実ぶりなどを中心に、全体として高い評価を得ることができた。いつ発生するか分からない自然災害や不注意による交通事故への対策など、命を守るための日常的な備えについて組織的に取り組んでいくことの重要性を肝に銘じていきたい。