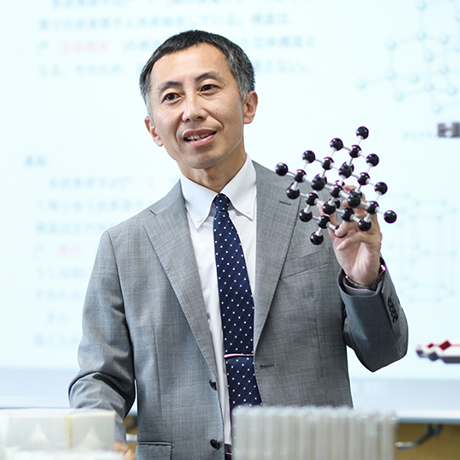好きなことに全力を注ぐ探究創造科の学び。
3年間で、生徒たちは驚くほど成長します。

探究的な学びに取り組む2つのコース
まず、探究創造科の概要を教えてください。
伊藤: 探究創造科には、「地域創造コース」と「科学情報コース」の2コースがあります。2つのコースに共通するのは、探究的な学びに力を注いでいることです。自分で課題を設定し、それを自分自身で調べたり研究したりして発展させるプロジェクト型学習が、大きな柱になります。金曜日の5、6時間目と隔週の土曜日がプロジェクト型学習の時間になっています。
四ツ谷: 地域創造コースは「地域を学ぶ」コースだと思われがちなのですが、実際は「地域で学ぶ」コースです。「地域について学ぶ」ということではなく、「地域で何を学ぶか」が重要な点で、生徒自身がそれを掘り下げていきます。
坂下: 科学情報コースは「科学の力で世の中をより良く」を目標としていて、地域の企業の方などいろいろな方たちに協力していただきながら、プロジェクト型学習を進めています。
伊藤: プロジェクト型学習の中身についてもご説明していきましょうか。
四ツ谷: 地域創造コースでは、「衣食住」の観点で探究的な学びを行います。たとえば「住」の観点では、浜松市の永田木材さんにご協力いただいて、森林の伐採現場を見学させてもらったり、木材を使ったノベルティ(イベントなどで配布するグッズ)制作を行ったりします。各プロジェクトの最後に必ず行われるのが、企業の方たちに向けたプレゼンテーションです。その評価も企業の方にお願いしています。制作したノベルティは実際に本校のオープンスクールで配られるのですが、そのように製品化が最終的なゴールになる場合もあります。
坂下: 科学情報コースでは「サイエンス」「プログラミング」「エンジニアリング」の3分野でプロジェクトに取り組みます。その一例として、「エンジニアリング」分野ではミニ四駆を教材に使い、パーツの組み合わせを変えたり改造を行ったりして、より速く走らせるための試行錯誤を行います。成果発表の際には株式会社タミヤの方にご協力いただき、評価をしていただいています。
生徒に対して「正解」は言わない。

取り組みの内容を聞いているだけでも楽しそうですね。
坂下: 生徒たちは本当に楽しそうです。みんな休み時間返上で続けるくらい、没頭して取り組んでいます。私たち教員が「休み時間だから一回手を止めて休もう」と声をかけているくらいです。地域創造コースも同じですよね。
四ツ谷: 同じですね。インプット型の学びとは真逆の、アウトプット型の学習ならではの楽しさを感じていると思います。
伊藤: 自分の考えやアイデアを形にして、それを企業や地域の方たちに向けて発信していく。そうした取り組みには、机の前に座って行う勉強にはない楽しさがあるのですね。
坂下: 使っている教材自体の面白さもあると思います。生徒にとって「こういうことが考えられるかも」とか「こういう風にしたらどうなるだろう」という発想を広げやすく、試行錯誤につながるような教材を選んでいます。私たちは「学びの余白」と言っているのですが、その余白の広さが面白さにつながっていると思います。
四ツ谷: 基本的に、私たち教員は生徒に対して正解を言いません。何かを教えるというより、少し助言をして気づかせるというイメージです。「生徒たちと一緒になって進んでいく」という、ある程度対等な協働プロジェクトの一員のような関係だと思っています。生徒たちがたどり着いた答えが重要だと思っています。
坂下:
科学情報コースでも正解をすぐに教えるということはしませんし、探究を深めていく中で、私たちの想定を超える成果が出てくる場合もあります。生徒たちは自分の好きなことをどんどん掘り下げていくので、「私より詳しくなっている」と驚かされることがあります。
生徒たちが自分で気づいたり調べたりすることによって、答えにたどり着くことが大事だと考えています。何かをやってみて失敗しても、もう一度挑戦することが重要だと思うので、私たちはそのきっかけを作る役だと認識しています。
四ツ谷: 生徒が成長する過程を見守ることが大切ですね。探究的な学びはそれができるフィールドだと思います。私が特に意識しているのは、生徒たちを認めることです。「合っている」とか「間違っている」という以前に、「いいじゃん、すごいじゃん!」と、まず意見を尊重する対話を意識するようにしています。
伊藤: 失敗をおそれずに挑戦できるのは大きいですね。先日1年生が、浜松の伝統的な染色技法である「注染染め」の体験をしたんです。染めた時は失敗したように思えたとしても、生地を洗って見てみたら案外きれいな色が出ていたりする。当初思い描いたものと違うものができても、それ自体を楽しむことが大切だと思います。
自分が高校生だったら通いたくなる学校

いろんなことに挑戦できる環境は魅力ですね。
伊藤: 探究創造科には「安心して失敗できる環境」があると感じます。注染染めの体験でも、誰か一人がやり始めると、次々に「やってみたい」と手が挙がります。中学校時代までの経験で、失敗に対して怖さを感じているかもしれませんが、みんなが「やりたい」という気持ちを表現するので、参加しやすいと思います。
四ツ谷: 実は、「中学時代まで学校があまり楽しくなかった」という生徒もけっこういるんです。そういう生徒は「もっと自分らしさを出したい」という気持ちを持って本校に入学してきます。期待していたことを実際に体験し、「自分を出してもいいんだ!」と気づいた時の表情の変化は、見ていてすぐに分かります。
伊藤: 生徒たちが本当にニコニコしながら、目をきらきらさせながら取り組む姿を見ると、「高校生ってこんなに楽しくやれるんだ」と感じますね。
四ツ谷: オープンスクールなどで説明すると、多くの保護者の方が「自分たちの頃にこういうコースがあれば良かった」と言ってくれることがあります。
坂下: よく「私が入りたいくらいです」って言われますよね。
四ツ谷: 我々教員も同じ気持ちで、自分たちの高校時代にはこういう体験ができる環境はありませんでした。「自分がもし今生徒として通ったら絶対に楽しい学校だな」と思いながら仕事をしているので、それが生徒に伝わるのだと思います。
坂下:
科学情報コースは、何かを突き詰めて取り組むという経験をした生徒が集まっているので、そうした姿勢で探究することが「特別」ではなく「スタンダード」になっています。たとえばプログラミングについても、高校入学後に初めて経験する生徒もいるのですが、その中でちゃんと成長して研究の成果を外部に発表しに行っています。多くの生徒が「好きなことをとことんやる」ということに魅力を感じているのだと思います。
ただ、好きなことだけやればOKという話ではなくて、自分の好きなことを探究していく中で、それをより深めていくために「必要な知識」や、「身につけた方がよい力」が見つかるので、教科の学習を進めていく必要が出てきます。そして、教科の学習で学んだことをまた探究的な学びに活かす。そうやってぐるぐると教科の学習と探究的な学びを回していきます。だからみんな、勉強もしっかり頑張っていますよ。「探究的な学び」と、「教科学習」を行き来しながら探究を深めていけることが、探究創造科の良さだと感じています。
ワクワクを形にできる人になってほしい

伊藤: ポスター発表を見ていても、私たちが知らないような言葉がたくさん出てきます。私たちが驚きを感じるくらい深く調べています。坂下先生が言うように、「好きなこと」と「教科学習」をちゃんと自分の中で回しているのだと感じます。
坂下: ポスター発表も、最初は慣れなくて「大丈夫かな?」と心配することもあるのですが、生徒の中で「もっとこうしたい」という気持ちが強くなっていって各自で練習を重ねています。最終的な成果発表の時はびっくりするくらい成長していて、見ていて感動すら覚えます。
探究創造科の学びが卒業後の進路や社会人生活にどうつながりますか?
坂下: 探究的な学びを通してジェネリックスキル(社会人基礎力)を育成することが目標の一つになっていますが、それに加えて大学入試にフォーカスすると、入試形態が変化してきていて自分の考えや意見を話す機会が増えています。探究創造科で自分の「やりたいこと」や「やってきたこと」を人に伝えてきた経験が、入試にも役立つと思います。
四ツ谷: そうですね。だから、推薦入試に強いですよ。(探究創造科で行っているような)深い内容の探究は、一般的に大学2年次以降に取り組むようなことです。それを高校時代に先取りして行っているので、大学からは即戦力になっているという評価もいただいています。 地域創造コースの生徒たちの進路は本当に多様で、経営、経済、地域政策、総合政策などの分野のほか、美大に行った生徒もいれば音楽系や医療系、体育系に進む生徒など、これまでのクラスでは考えられないほど多岐にわたります。
伊藤: これからの時代は、自分の思いや考えを発信する力を身につけないと、世の中を渡っていくことはできません。そういう時代に求められる力、社会を生きていく上で必要な力が育まれていると感じます。 生徒たちには県外の大学に行くなどしてさらに学びを深めてほしいと思いますが、大学卒業後はぜひ地元の浜松に戻ってきてほしい。高校時代に培った「地域で学ぶ」経験や学びの成果を発揮し、持続可能な地域づくりに貢献してくれることを期待します。
どういう思いや個性を持った人に入学してほしいですか?
坂下: 科学情報コースは「突き詰めて一つのことをやりたい人」はもちろん、「幅広くいろんなことに興味を持っている人」にも適したコースだと思います。何かに対して興味・関心を抱いて、それを自分の手で深めたいという好奇心。私たちは「わくわく」と言っていますが、好奇心を持って何かに取り組むことができる人は楽しく3年間を過ごせると思います。「好奇心(わくわく)を形にできる人」になってほしいですね。
四ツ谷: 協働できて対話できる人ですね。地域創造コースの探究的な学びは、一人で行う活動ではなく必ず協働します。複数人でチームを組んでプロジェクトに取り組み、終わったらチームを解体して別のチームを組む。そういうことを繰り返し行うので、プロジェクトに興味があるのはもちろん協働や対話ができる人にぜひ入学していただきたいと思います。
伊藤: 探究創造科は、自分のやりたいことを見つけて、仲間と一緒に探究・研究をしていく科です。勉強にもしっかり取り組みながら探究的な学びを楽しみたい、という人に来ていただきたいと思います。